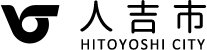療養の給付(お医者さんにかかったとき)
被保険者の皆さまが病気やケガによって医療機関を受診する際に、被保険者証を窓口に提示することによって、療養の給付を受けることができます。
その給付は、診療を受けた医療費総額に対し、次に示す給付割合に応じた金額を医療機関に直接支払うことで行われます。
よって、被保険者の皆さまは、自己負担割合に応じた医療費を医療機関にお支払することで診療を受けることができます。
| 年齢区分 | 給付割合 | 自己負担割合 |
|---|---|---|
| 小学校就学前 | 8割 | 2割 |
| 小学校就学以上70歳未満 | 7割 | 3割 |
| 70歳以上75歳未満 | 8割若しくは7割 | 2割若しくは3割 |
また、入院時に発生する食事代については、食事療養費が支給されます。その支給方法は、次に示す自己負担金額を除いた金額を医療機関に直接支払うことで行われます。
なお、住民税非課税世帯または70歳以上で区分Ⅰ、Ⅱの方は、医療機関に「標準負担額限度額認定証」の提出が必要となりますので、入院の際は国保年金係で申請を行ってください。
住民税課税世帯(一般)の方
1食 460円
住民税非課税世帯または区分Ⅱの方
- 90日までの入院・・・・・・・・・1食 210円
- 過去12ヶ月で90日を越える場合・・・1食 160円
区分Ⅰの方
1食 100円
療養費の支給(全額自己負担したとき、あとで払い戻されるもの)
次のような場合は、被保険者は医療費をいったん全額負担していただくことになりますが、あとで国保の窓口で申請し審査で決定すれば、自己負担額を除いた額の払い戻しが受けられます。
- 旅先で急病になり保険証を持たずに診療を受けたとき
<必要なもの>保険証・領収書・診療内容の明細書・印かん・世帯主の口座番号 - お医者さんが治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を購入したとき
<必要なもの>保険証・領収書・医師の装着指示書等・印かん・世帯主の口座番号 - 医師の指示で、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
<必要なもの>保険証・明細な領収書・医師の同意書・印かん・世帯主の口座番号 - 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
<必要なもの>保険証・明細な領収書・印かん・世帯主の口座番号 - 重病の人などが、治療を受けるために移送されたときの車代などを支払ったとき(医師が必要と認めた場合に限る)
<必要なもの>保険証・領収書・医師の証明書・印かん・世帯主の口座番号 - 手術などで輸血に用いた生血代(注:提供者が親族以外)
<必要なもの>保険証・輸血用生血液受領証明書・医師の診断書か意見書・印かん・世帯主の口座番号・血液提供者の領収書 - 保険税滞納による「資格証明書」で受診して全額自己負担したとき
<必要なもの>資格証明書・領収書・診療内容の明細書・印かん・世帯主の口座番号 - 海外渡航中の診療を受けたとき
<必要なもの>保険証・領収書及び日本語訳文・診療内容の明細書及び日本語訳文・印鑑・世帯主の口座番号
高額療養費
医療費の自己負担額には世帯の前年の所得に応じた限度額が設けられています。詳しくは、下記リンクよりご確認いただけます。
その他の給付
1 出産育児一時金
408,000円(1子につき)
但し、産科医療補償制度に加入している医療機関で分娩した場合は、12,000円を加算します。
国保被保険者が出産されたとき、その方に支給します。
<必要なもの>保険証・印かん・母子健康手帳・出産費用の明細書・出産者の口座番号
支給方法は、出産育児一時金直接支払制度と償還払いの2とおりがあります。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産、流産も支給されます。(その場合は、医師の証明書が必要です。)
2 葬祭費
20,000円
被保険者が死亡されたとき、葬儀を行った方(喪主)に支給します。
<必要なもの>保険証・印かん・喪主の口座番号