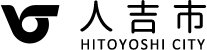1ヶ月の医療費の自己負担(一部負担金)が高額になったときは、国民健康保険から高額療養費が支給され、医療費自己負担が軽減されます。
高額療養費が適用される自己負担限度額は、それぞれの世帯の収入により区分設定されています。
また、一医療機関での入院若しくは外来が自己負担限度額を超えるような場合は、医療機関に限度額適用認定証を提示することで、医療費自己負担を限度額までの支払いとすることができます。また非課税世帯の方は食事代の減額も受けることができます。
| 所得区分
(国保加入世帯員の前年所得合計) |
3回目までの自己負担限度額 | 4回目以降の限度額(注1) |
|---|---|---|
| 旧ただし書所得(注2) 901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1 % | 140,100円 |
| 旧ただし書所得 600万円から901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1 % | 93,000円 |
| 旧ただし書所得 210万円から600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1 % | 44,000円 |
| 旧ただし書所得 210万円以下 | 57,600円 | 44,000円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
(注1)過去12ヶ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
(注2)旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です。
自己負担額の計算方法
- 月の1日から末日までの1ヶ月ごとの受診について計算します。
- 同じ病院等で複数の診療科がある場合、歯科は別計算となります。
- 一つの病院・診療所ごとに計算します。
(病院・診療所が違う場合は、合算できません) - 一つの病院・診療所でも、入院と外来は別計算となります。
(外来は、診療科ごとに計算する場合があります) - 他の病院の医療費自己負担が21,000円を超える場合は、合算して計算することができます。
- 院外処方で受けた調剤自己負担は、処方せんを発行した病院等の自己負担と合算します。
- 差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除きます。
- 入院時の食事代の標準負担額は除きます。
高額療養費の申請(自己負担限度額を超えて医療費を負担した場合)
- 持参するもの:医療費の領収証、世帯主の銀行口座番号(通帳等)、世帯主の認印、身分を証明するもの(マイナンバーカードや運転免許証)
- 申請窓口:市民課 国保年金係(2番窓口)
限度額適用認定証の交付申請
- 持参するもの:世帯主の認印、身分を証明するもの(マイナンバーカードや運転免許証)
- 申請窓口:市民課 国保年金係(2番窓口)
入院時の食事代負担額
| 所得区分 | 入院時の食事代(1食当たり) | ||
|---|---|---|---|
| 住民税課税世帯 | 510円 | ||
| 住民税非課税世帯 | 90日までの入院 | 240円 | |
| 90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数)
届出必要 |
190円 | ||