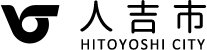プラスチックは、私たちの生活に欠かせない素材である一方で、海洋プラスチック問題や気候変動問題への対応を契機としてプラスチックの資源循環を促進していく重要性が高まっています。
こうした背景から、令和4年4月に、「プラスチック資源循環促進法」がスタートし、プラスチックの製造から、ごみとして処理されるまでに関わるすべての事業者、自治体、住民がプラスチックの資源循環に取り組むこととされており、自治体においては、家庭から出るプラスチックごみの分別収集・リサイクルに努めることとされています。
そのため、人吉市では、更なるごみ減量や温室効果ガスの削減のため、令和7年10月から市内全域でのプラスチック類の分別収集を実施します。
プラスチック類で出せるもの(プラマーク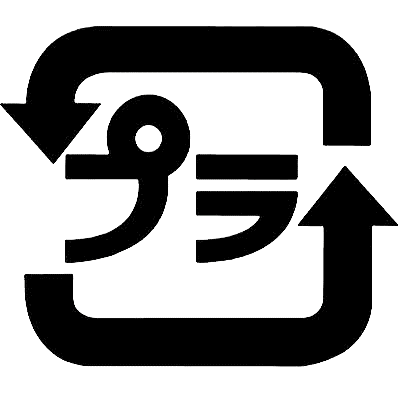 が目印)
が目印)
容器・キャップ・ラベル類
【例】洗剤容器、シャンプー容器、化粧品や日用品の容器、食用油のボトル、ペットボトルのキャップ、ラベル
カップ・パック類
【例】卵パック、豆腐のパック、、納豆容器、プリンやヨーグルト、アイスなどのカップ、ハムやソーセージなどのパック、菓子やカップ麺などの外装フィルム、生鮮食品や弁当などのラップ
チューブ類
【例】マヨネーズ等の容器、歯磨き粉
トレイ(皿型容器)類
【例】弁当や惣菜などのトレイ、白色等のトレイ
食料品や日用品の袋類
【例】お菓子等の食品袋、洗剤等の詰め替え用袋、ビニール袋
発泡スチロールなど
【例】発泡スチロール、緩衝材、みかんや玉ねぎなどのネット袋
プラスチック製品
【例】バケツ、ハンガー、じょうろ、ストロー、フォーク、スプーン、プラモデル、歯ブラシ、CD(本体)、ケース、計量カップ
プラスチック類で出せないもの
(出典元「日本容器包装リサイクル協会)
特に注意(発火や怪我などの危険性があるもの)
以下の製品は、発火やけがの危険性がありますので、絶対にプラスチック類で出さないでください。
- 充電式電池内蔵製品(加熱式たばこ・ハンディファンなど)
- ライター
- 注射器
- 刃物類
(出典元「日本容器包装リサイクル協会」)
プラスチック類の分別方法(見分け方)
プラスチック類の出し方
【チューブ類】
【ボトル類】
【カップ類】
【トレイ類】
【詰め替え用容器・レトルト食品パック】
(出典元「日本容器包装リサイクル協会」)
Q&A
Q1:収集したプラスチック類はどうなるの?A2:出来るだけはがしていただきますが、はがれにくい場合は、そのままでも出せます。
Q3:なぜ、ペットボトルは分ける必要があるの?
A3:ペットボトル(本体)は、二酸化炭素の削減に向けたサントリーとの協定により、繰り返しペットボトルにリサイクルされるため、キャップとラベルは「プラスチック類」、ペットボトル(本体)は「ペットボトル」として別の袋に分けて出してください。
A4:厚みのあるプラスチック(厚さ5ミリメートル程度以上が目安です)は、リサイクル施設の破砕機を損傷させるおそれがあるため、出せません。これまで通り、燃えるごみとして出してください。
A5:ネットを被せたり、袋と袋を結ぶ等、各自でごみが散乱しないような対策をお願いします。
A6:スーパーやドラックストア等で販売している市販の45リットル以下の透明または半透明で中身が確認できる袋を使用してください。ただし、人吉市指定の「燃えるごみ袋」、「燃えないごみ袋」は使用できません。
- 自分の出したごみを引き取る。
- シールに書かれた注意項目を確認し、指示に従って再分別等を行う。
- 再分別等が済んだら、決められた日時・集積所に改めてごみを出す。