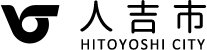未曽有の豪雨災害から5年を迎えるにあたり、令和2年7月豪雨災害で犠牲となられた方々を追悼すること及び災害を風化させないことを目的に令和2年7月豪雨犠牲者追悼式を執り行いました。
日にち:令和7年6月29日(日曜日)
場所:市役所庁舎 1階市民ホール
追悼式次第
午前10時 黙とう
- 献奏
- 主催者式辞
人吉市長 松岡 隼人
- 来賓のお言葉
熊本県知事 木村 敬 様
衆議院議員 金子 恭之 様
参議院議員 松村 祥史 様
- 追悼のお言葉
境目 悠真 様
- 献花
人吉市長 式辞
本市に壊滅的な被害をもたらした令和二年七月豪雨災害から、早くも5年の歳月が過ぎようとしています。
本日ここに追悼式を挙行するにあたり、御遺族ならびに大変御多忙の中、熊本県から木村知事、地元選出の金子代議士、松村参議院議員をはじめ、多数の御来賓の皆様の御臨席を賜り、心からお礼申し上げます。
本市では、災害関連死を含め21名のかけがえのない命が犠牲となりました。御遺族の皆様におかれましては、最愛の御家族を突然失われた悲しみはあまりにも深く、もう一度会いたいとの追慕の念が消えることはないものと存じます。改めて、犠牲となられた皆様に哀悼の誠を捧げ、心からお悔やみを申し上げます。
毎年この季節が近づくと、あの日、まちを飲み込んだ濁流の轟音や湿った泥のにおい、一夜にして変わり果てたふるさとの景色が、昨日のことのようによみがえり、今でも胸が苦しくなります。あの日のような悲劇は二度と起こってほしくないと願いながらも、いつまた起こるかわからない不条理な災害に備えて、この5年間、安全安心なまちづくりを目指し、取り組んでまいりました。
おかげをもちまして、国・県をはじめ多くの皆様の御支援によって、復旧・復興への歩みも着実に進み、本年2月には市内最初の避難路である温泉町地内第1号線の工事が無事完了しました。
また、早期避難に役立てるため、地域に即した防災行動計画である「コミュニティタイムライン」の作成を進め、現在31の町内会に備えることができました。
この人吉に住む人々の命と財産を守ることを第一義として、「逃げ遅れゼロ」のための避難体制づくりを確立してまいります。そして、この先も変わらず愛する球磨川とともに生きていくため、命と清流を守る「緑の流域治水」への取組を、国・県・流域市町村と連携し、推し進めてまいります。
災害直後に整備された木造仮設住宅を県から無償譲渡いただき、市営の利活用住宅として、本年4月から供用を開始することができました。また東校区に2棟の災害公営住宅が完成し、応急住宅からこれらの恒久的な住まいへ移された方は、144世帯220人となり、一歩一歩、復興が進んでいることを実感しています。
一方で、被災された方は今もなお、それぞれに様々な悩みや課題を抱えておられます。その御労苦が少しでも和らぎ、希望をもって暮らしていただけるよう、最後の一人まで寄り添い続けてまいります。
災害からの復興は、単なる元の状態への回復にとどまらず、「ここに残りたい、ここに住み続けたい」、さらには「行ってみたい」と思っていただけるまちづくりが必要です。本市では、本年3月に、災害から学んだ教訓と、未来への希望を込めて「人吉市まちなかグランドデザイン推進アクションプラン」を取りまとめました。このアクションプランは、本市に生きる人々の暮らしとなりわいの復興、その先の魅力・活力あふれるまちづくりの道しるべとなるものです。ここに描いた未来の実現には、市民の皆さまの御協力が不可欠です。被災され辛苦を抱えられながらも、この人吉に留まり、また故郷に戻ってこられ、まちの再興の担い手として真摯に前を向いて来られた市民の皆様に、改めて敬意と感謝を申し上げたいと存じます。犠牲となられた方々にも胸を張って御報告できる人吉にしていくために、全力を尽くしていくことをここにお誓いいたします。
結びに、犠牲となられた皆様が安らかにお眠りになられますことを改めてお祈り申し上げるとともに、御遺族並びに御臨席いただきました皆様の御健勝、そして本市の将来に御加護を賜りますよう心からお祈り申し上げ、私の追悼の言葉といたします。
令和7年6月29日 人吉市長 松岡 隼人
追悼のお言葉(境目 悠真様)
令和2年7月豪雨災害から、まもなく5年の歳月が経とうとしております。
本日ここに、追悼式が執り行われるにあたり、代表して、謹んで追悼の言葉を申し上げます。
当時、私は中学校に入学したばかりで、新型コロナウイルス感染症の影響による休校も重なり、不安の多い日々を過ごしていました。
7月4日、両親の慌てた声で目を覚ますと、テレビから球磨川が人吉の街を飲み込む信じがたい光景が繰り返し流れていました。これが本当に今、人吉で起きていることなのか、何度も両親に確認したのを覚えています。中学生だった私は、ただ見ていることしかできず、子どもながらに無力さを痛感しました。
幸い、自宅には被害がありませんでしたが、父が下青井町で経営していた美容室は、天井近くまで浸水しました。父は早朝、お店の様子を見に出かけましたが、危険を感じ帰ってきました。帰宅途中に道路が冠水し始め、車のタイヤが水に浸かりながら帰ってきたと聞きました。水が引いてから片づけに向かうと、店内は泥にまみれ、備品は散乱し、見る影もない状況に胸が痛みました。改めて、父が無事であったことに安堵すると同時に、一歩違えば命を落としかねない状況だったのだと、とても恐ろしくなりました。
片付けを手伝う中で、周囲の被災された方々とお話しする機会がありましたが、「家がなくなって、これからのことが何も考えられない」と途方に暮れておられる方に、かける言葉が見つかりませんでした。水没した家財道具が次々と運び出され、道路沿いに堆く積みあがっていく様子や、必死に泥をかき出し、疲れ切った皆さんの表情が目に焼き付いています。自分の中に湧き上がる喪失感に触れ、いつも賑わっていたお店が、街が、人吉が、当たり前だと思っていた日常が、どれほどかけがえのないものだったか、強く実感しました。そして同時に、家族や友人といった身近な人々がいてくれることの尊さを深く感じました。
私がこの経験を通して伝えたいことは、「自分事として捉えることの大切さ」です。私も学校で過去の災害について学んだことはありましたが、どこか他人事のように感じていたのも事実です。あの日も「いつもより強い雨だな」と感じてはいたものの、ほとんどの人が、これほどの未曾有の災害になるとは思っていなかったのではないでしょうか。
自然の力は想像を超えるほど大きく、その前に人間はあまりにも無力です。しかし、情報を得て正しく備えることは、自らを守るための力になります。全国には、まだ災害を自分事として捉えていない人が多くいるかもしれません。近年は地震なども頻発しており、誰しもが常に災害の危機と隣り合わせです。
昨年10月、高校の仲間とともに「世界津波の日 高校生サミット」に参加し、豪雨災害の経験を国内外の高校生たちと共有し、防災や復興について語り合う機会を得ました。このような交流を通じて、経験を伝え、学び合うことの大切さを強く感じました。
私たち自身が、経験を語り継ぎ、自ら考え、過去から学ぶ姿勢を持ち続けることで、この災害の記憶を風化させることなく伝え続けていくことができると信じています。一人ひとりの意識と行動が、きっと誰かの命を守る力となるはずです。災害に苦しむ人が少しでも減る社会の実現に向けて、私も自分にできることが何か考え、力を尽くしていきたいと思います。
最後になりましたが、改めまして、これまでご支援をくださった皆様、復旧・復興に携わっていただいた皆様に深く感謝を申し上げます。
令和2年7月豪雨災害で尊い命を落とされたすべての方々の御霊が安らかならんことを心よりお祈り申し上げますとともに、私たちはその方々の思いを胸に、未来に向けて歩み続けていくことを誓い、追悼の言葉といたします。
令和7年6月29日 代表 境目 悠真
献花台設置
日時:令和7年6月30日(月曜日)から7月4日(金曜日) 8時30分から17時
場所:市役所庁舎 1階市民ホール
73名の方に献花いただきました。
(注)献花の際に一部の方からいただきました献花料につきましては、令和2年7月豪雨災害見舞金として寄付させていただきました。