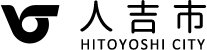令和8年度の保育所・認定こども園・幼稚園への入所申込受付が始まります。入所を希望される方は、下記のとおりお申し込みください。
利用の流れ
保育所・認定こども園・幼稚園(子ども・子育て支援新制度移行園のみ)の利用を希望する保護者は、利用のための認定を受ける必要があります。
| 認定区分 | 対象年齢 | 内容 | 利用先 |
|---|---|---|---|
| 1号認定 | 満3歳以上 | 教育標準時間認定 | 幼稚園(新制度移行園のみ)、認定こども園 |
| 2号認定 | 満3歳以上 | 保育認定 | 保育所、認定こども園 |
| 3号認定 | 満3歳未満 | 保育認定 | 保育所、認定こども園 |
教育標準時間認定(1号認定)…教育を希望される場合
保育認定(2号認定・3号認定)…「保育の必要な事由」に該当し、保育を希望される場合
教育標準時間認定について
- 幼稚園・認定こども園に直接利用を申し込む。
- 幼稚園・認定こども園から入園の内定を受ける。
- 幼稚園・認定こども園を通じて、市へ利用のための認定を申請する。
- 幼稚園・認定こども園を通じて、市から認定証が交付される。
- 幼稚園・認定こども園と契約を行う。
保育認定について
保育所・認定こども園での保育を希望する場合は、「保育を必要とする事由」に該当することが必要です。また、保育認定(2号認定・3号認定)は下記の基準を用いて判断します。
1 保育を必要とする事由
- 就労(フルタイム、パート、夜間、内職、自営業などすべての就労)
- 妊娠、出産(母が出産月の前後8週間の場合)
- 保護者の病気や障がい
- 同居または長期入院等をしている親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む、最大3か月まで)
- 就学(職業訓練を含む)
- 虐待やDVの恐れがあること
- その他、上記に類する状態として市が認める場合
現在すでに保育所・認定こども園へ入所中の児童(2号認定・3号認定に該当)がおられる保護者で、育児休業を取得される場合において、次のいずれかに該当する場合は継続して入所ができます。ただし、新規入所の場合は該当しませんのでご注意ください。
- 次年度に小学校への就学を控えているなど、入所児童の環境の変化に留意する必要がある場合
- その児童の発達上環境の変化が好ましくないと考えられる場合
同居の親族が児童を保育することができる場合、利用の優先度が調整される場合があります。
2 保育の必要性
就労を理由とする利用の場合、下記のいずれかに区分されます。
| 利用区分 | 保育時間 | 要件 |
|---|---|---|
| 保育標準時間利用 | 最長11時間 | 保護者のいずれもが月120時間以上の就労である場合 |
| 保育短時間利用 | 最長8時間 | 保護者が月48時間以上月120時間未満の就労である場合 |
- 就労を理由として、保育所・認定こども園を利用するためには、保護者のいずれもが月48時間以上の就労が必要となります。いずれかが下回る場合は入所できません。
- 就労時間が変更になった場合は利用時間の見直しを行う場合があります。
3 「優先利用」への該当の有無
ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業、お子さんに障がいがある場合などは、保育の優先的な利用が必要と判断する場合があります。
入所申込みについて
令和8年4月1日から新しく保育所・認定こども園・幼稚園(新制度移行園のみ)への入所を希望される方は、令和7年11月4日(火曜日)から令和7年12月19日(金曜日)までに申請書に必要書類を添えて、第一希望の利用施設に申し込んでください。
また、人吉市外の保育所・認定こども園・幼稚園(新制度移行園のみ)への広域入所もできます。ただし、希望される市町村・保育所・認定こども園・幼稚園(新制度移行園のみ)によっては、入所できない場合があります。広域入所をご希望の場合は、市こども未来課へ申し込んでください。
- 「申請書」、「入所申込みの手引き」等の書類は、市内の各保育所・認定こども園・幼稚園および市こども未来課に備えてあります。申込みの際は、「入所申込みの手引き」や「記入例」をよく読んで手続きしてください。
人吉市認可保育所・認定こども園・幼稚園一覧 (PDF 119KB)
入所選考と決定
希望の保育所・認定こども園・幼稚園(新制度移行園のみ)への入所は、申請書類により入所基準の審査を行い決定します。入所申込みをしても、希望者多数の場合や、入所基準に該当しない場合は希望の保育所・認定こども園・幼稚園(新制度移行園のみ)に入所できない場合があります。また、保育の必要な理由によっては、保育期間の希望に添えない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
- 入所申し込みは、児童一人につき1か所です。重複申し込みはできませんのでご注意ください。
- 提出された書類で、就労状況や家庭状況、児童の状況などがわからない場合は、面接を行います。
- 受付期間に申し込みをした方には、令和8年3月中に入所の承諾・不承諾及び保留をお知らせします。
必要書類
申し込みには下記の書類がすべて必要です。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 教育・保育給付認定申請書 | 児童1人に1部必要です。 |
| 保育が必要であることを証明する書類(2号認定・3号認定のみ) | 父母についての左記書類が必要です。 |
保育が必要であることを証明する書類(2号認定・3号認定のみ)
保育が必要である事由によって、提出書類が異なります。どの提出書類が必要であるかは「令和8年度入所申込みの手引き」でご確認ください。
保育料及び副食費について
- 1号認定の児童及び2号認定の児童のうち令和8年4月1日現在の満年齢が3歳から5歳(年少クラスから年長クラス)までの児童の保育料は、令和元年10月から実施されている幼児教育・保育の無償化により、無償化されています。
- 1号認定の児童及び2号認定の児童のうち令和8年4月1日現在の満年齢が3歳から5歳(年少クラスから年長クラス)までの児童は、保育所・認定こども園・幼稚園(新制度移行園のみ)が設定する副食費を、保育所・認定こども園・幼稚園(新制度移行園のみ)にお支払いください。副食費の免除対象者は、保護者の令和7年度市町村民税額及び令和8年度市町村民税額で決定します。
- 令和8年4月1日現在の満年齢が0歳から2歳までの児童の保育料については、保護者の令和7年度市町村民税額及び令和8年度市町村民税額で決定します。
- 保育料及び副食費は、令和8年4月から8月分は令和7年度市町村民税額、令和8年9月から令和9年3月分については令和8年度市町村民税額で決定します。また、父母が同居の祖父母等の収入により生計を立てている場合や、祖父母等の税法上の扶養に児童もしくは父母が入っている場合など、祖父母等が家計の主宰者である場合には、祖父母等の税額も合算して保育料及び副食費を算定します。
- 保育料及び副食費の決定の際の住民税額については、住宅取得控除・配当控除・外国税額控除等の適用はしません。
- 入所後に税額や世帯員の変更が生じたとき、または結婚・離婚など戸籍の届出や生活保護の開始・廃止が生じたときは、保育料または副食費が変更となる場合があります。市こども未来課へご連絡ください。
- 保育料は各月の初日が在籍の基準日となりますので、在籍した月は、出席日数にかかわらず1か月分の保育料が必要となります。
- 確定申告や市民税申告(令和7年中に所得がなかった方も含む)の対象になる方につきましては、期限内に必ず申告してください。未申告の場合、保育料または副食費を決定するための税情報が確認できませんので、保育料を「最高額」で算定させていただきます。
入所後の届出について
下記のような場合は、申請中・入所中を問わず市こども未来課へ必ず届け出てください。
- 家庭内保育が可能となったとき(退職、病気治癒、育児休業取得、その他) 2号認定・3号認定のみ
- 転出するとき
- 世帯の状況が変わったとき (離婚により母子・父子世帯になった、住所・氏名が変わった等)
- 所得税額が変わったとき(期限後の税の申告(確定・修正)など)
- 生活保護が開始・廃止されたとき
退所していただく場合があります
- 虚偽の申込みや届け出があった場合
- 入所理由が消滅した場合(退職、病気治癒等) 2号認定・3号認定のみ
- 入園児童が心身の状況等により集団保育になじまない場合
- 継続して1か月以上保育所・認定こども園・幼稚園(新制度移行園のみ)を欠席した場合、または無断欠席が同月内で連続して2週間以上続いた場合
- 2号・3号で保育所・認定こども園に入所される方で、求職を理由に入所できる期間は3か月です。期間内に就労証明書等を提出されない場合は、入所を解除されますのでご承知おきください。
なお、退所するときは、必ず退所する月の25日までに「退所届」を提出してください。
保育所・認定こども園・幼稚園への継続入所について
現在すでに市内の保育所・認定こども園・幼稚園へ入所中の児童で、来年度も引き続き同じ保育施設等への継続入所を希望する場合は、「継続入所申請書」の提出が必要です。
- 「継続入所申請書」は、令和7年11月4日(火曜日)から令和7年12月19日(金曜日)までに、現在入所中の保育施設等へ提出してください。
- 「令和8年度入所申込みの手引き」で添付書類等を確認してください。
令和8年度入所手引き等について
- 令和8年度入所申込みの手引き (PDF 534KB)
- 就労証明書 (Excel 58KB)
- 就労証明書(手書き用) (PDF 182KB)
- 求職中の申立書 (Word 28KB)
- 求職活動証明書 (Word 36KB)
就労証明書について
就労証明書は国標準様式の就労証明書を使用します。電子データは上記よりダウンロードしてご使用ください。手書きで作成される場合は、上記より出力した様式に記入していただくか、各保育施設および市こども未来課に備えております手書き用様式をご使用ください。
- 就労証明書はお勤め先の事業所で作成してもらってください。
- 押印は不要です。
- 記載内容について確認する場合がありますので、必ず記載者氏名と記載者連絡先をご記入ください。
- 就労予定の場合も同様式をご使用ください。証明日が雇用開始日よりも前の日付である場合、就労予定として判断します。
(注)自営業・農林水産業従事者の提出書類について、就労証明書及びその証拠となる書類の提出に変更しており、民生委員児童委員意見書は不要になります。就労証明書はご自身で作成し、事業所名にはご自身の名前を記入してください。